 |
|
 |
 |
[結核・非定型抗酸菌症治療]
 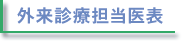
|
 |
| |
結核・非定型抗酸菌症 肺結核は減少を続けていますが、時おり新聞、テレビで報じら
れるように結核の集団感染、院内感染があります。
また健康診断や職場検診で結核が発見されたということがあります。
2週間以上続くがんこな咳、痰のあるときは結核を疑うようにいわれますが、時には検診
発見のようにまったく自覚症状がなくみつかることがあります。
結核は早く発見し、正しく治療すれば、今日ではなおせる病気になりました。
問題は診断と治療が適切に行われなければならないし、普通の感染症よりは長く治療を
守ってもらわなければなりません。
正しく診断されても、途中で治療を中断されますと、いわゆる耐性菌が発現してなおすのに
難渋するようになります。
本院は伝統的に結核治療に取り組んできましたので、診断のための検査法は完備し万一
他へ感染の恐れのある時の入院治療も出来ます。
時に結核菌と混同して非定型抗酸菌症が発見されることがあります。
これははじめに咳痰の顕微鏡検査をする時、両者は形態的に鑑別がつかないからです。
胸部X線検査でも時に両者の鑑別が困難なことがあり、この場合は最悪の場合を想定
して「結核症」として対応することになります。
その後に行う精密検査ではじめて「非定型抗酸菌」と同定され診断が確定します。
非定型抗酸菌は人から人への感染の恐れは通常ありません。 従ってこの点が「結核症」
と異なることで、非定型抗酸菌であれば感染防止のために入院していただいたり、職場を
はなれなければならないことはありません。
非定型抗酸菌は実は自然界、土壌や水道水にも存在するもので、たまたま気管支
拡張症や肺結核治療時などに肺のなかに住みやすい空間があるとそこに定着してしまう
ものです。
菌量が少なければ共生しているくらいに考えていてもよいものです。
治療法は感染症ですから抗生物質による化学治療です。 非定型抗菌症は頻度の
低いものも含めておよそ10種類くらいあり、多くはなかなか抗生物質がきかないものが多い
ものです。
菌量が少なければ、あるいは出来れば菌量が増えないような治療法をめざしていくほか
ありません。
非定型抗菌症は最近診断法が進歩したので発見されることが多くなりましたが、やはり
頻度の低い感染症です。
本院では結核治療と合わせて、的確な診断と治療を行っています。
|
|
|